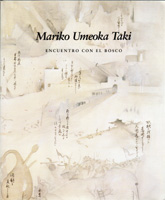|
||
≪カタログ中のテキストの抜粋≫ |
||
瀧梅岡 真理子 1987年7月、あんなにも避けていたスペインに自分の絵が瀕死の状態にあることを感じ初めて足を踏み入れる事になった。何故そんなに避けていたのかと言うと、それまで見たこともないのだから何の根拠もないのだが、ある直感があってどうしても関わりたくなかった。自分の絵に起こった問題の出口を探しているうちにグレーの時間をさまようようになり、ここから脱出するには、今まで避けていたものに接する事、嫌だと思ったところへ行き、嫌だと思った事を全部したら可能かもしれないと思い、決心した。 ・・・・・・・ そして、プラド美術館を歩き回り、私は本当は前から知っていた結果の前に立ち止まり、やっぱりこの苦い杯をイエズスのように飲まなくてはならないのかとため息をついた。もうどう考えても疑いようもなかった。ボッシュ作快楽の園の中にこの扉を開ける鍵がある、そんな確信を持てることなんて、人生の中になかなかないし、すべての画家に与えられるものではないので、ついに決心した。 ・・・・・・・
|
||
ハビエル・ルイス(スペイン外務省セルバンテス基金研究所エジプト所長・考古学者) ・・・・・・・ 瀧梅岡真理子は、5年の歳月をかけてボッシュの「快楽の園」を考察にし、研究し、そして、描くという比類のない課題に没頭した。これは芸術そのもの自体より芸術を生み出すという現代における芸術の範疇に完全に位置するものである。この期間、梅岡は常に謎に包まれたこの庭園の危険な道を散策したが、生粋の日本人の態度でもって、禅仏教の枯山水を思い起こす構成の下に、作品に透明な水、露及び湿り気というものを再現した。ボッシュ特有の雰囲気の中で画業に専念し、梅岡はとっておきの日本芸術の秘密を本来の伝統の外においていかに効果的に作用せしめるかということを我々コンテンポラリーの傍観者に打ち明けている。湿気、乾き、無の空間、雲も池も噴水も真の水を含んでいるわけではないが、それはあたかも本物のボッシュが丁度アトリエから出て来たみたいである。刷新されたボッシュであり、我々と同時代のものに見事に変わり、現代と同じ本性に駆り立てられて創作している。このことは、新しい「快楽の園」の創作者瀧梅岡真理子をして非常に現代的な作家にしている。
|
||
アントニオ・フェルナンデス・デ・アルバ ・・・・・・・・ 多くの犠牲を払い、自分自身の内面からの認識に満ちた、描くという行為に於いて、絵のデッサンに時間を惜しむことはできない。生れ出た絵は、心の奥底を写すような線描のメタファーや、ベールに被われた幾何的輪郭や、夜のうちにかすかに姿を現す星座のみが小さな光の穴を開ける暗い森や、奪回された時間的宇宙や、平行六面体の大都市や、思い出のしるしを伴った事物の素描や、あるいは、忘却のかなたの薄闇の中の生命の謎とその本質にも広がっていくのである。
|
||
イグシオ・ゴメス・デ・リアニョ(コンプルテンセン大学教授〔美学〕、文学者、美術評論家) ・・・・・・・ 瀧梅岡真理子の手になる、ボッシュの「快楽の園」の、クリスタルガラスのような驚くべき複製を見ながら、私は全身質問の固まりであった。この日本人の女性画家がこれほど執拗に捜し求めてきたものは何なのか。ある挑戦に対する答えを出したかったのか、それとも、ものすごく奇抜なことをやりたいと考えたのか。多分、ボッシュがたどったプロセスを再び体現しようとしたのではないか。 ・・・・・・・・ 真理子はあの原型をもう一度具現化しようと望み、彼女の筆があふれるように生み出す曙のような風景を生き生きと感じとることで、楽園の新しい女主人であるかのように感じたのではないだろうかと、私は心の中で問いかけていた。 ・・・・・・・・ 「園のどの部分が最もよく自分を表現していると思う?」と聞いてみた。
|
||
パブロ・ヒメネス(マフレ文化財団館長・美術評論家) ファン・アリニョから初めて瀧・梅岡真理子の話を聞いた時、正直言ってその印象は鮮烈だった。 ・・・・・・・ ある若い一人の日本女性が、彼女の感性にとっては無愛想で敵意に満ちていて、知人もなく、初歩的な必要最小限の言葉さえも知らない国へ全てを捨ててやって来た。そして、回りの世界や現実から隔絶して、5年もの長い間、パレスホテルとプラド美術館の間を歩いて往復するだけの生活を意志的に続け、北方のプラバンテ出身の、はるか昔の15世紀の画家の一枚の絵(彼女の感性にとっては無愛想で敵意に満ちた絵)を綿密にきちょうめんに再現したのである。 ・・・・・・・ その絵の模写をやることからたとえ一分でも気持ちをそらさないために、絶え間のない努力を続けたのである。これは、おおげさで、無謀で、やちゃな話であるが、また、謎と神秘に包まれた神々の物語の、魔法のこだまにふれて呼び醒ますような行動や体験が常に持つ、押さえようのない思いがけない力を秘めた、ひっそりとした沈黙の物語でもある。 ・・・・・・・
|
||
マヌエラ・メナ(国立プラド美術館前副館長、現パトロナート) プラド美術館にあるボッシュの絵の、瀧梅岡真理子による巨大な模写作品快楽の園は、最初、信じ難いものをみているという驚きの念を起こさせる。時間に追われ、一瞬の感情に左右されて動く現代社会にあって、昔の絵の師匠(マエストロ)、それも、几帳面で精密で、細部にまで気を配り完璧家であった中世のフランドルのマエストロが持っていたような名人芸、辛抱強さ、根気を持つ者がいるなどと信じることができないのである。この大変に若く並外れた日本人画家の、偉大なるトリプティカの色調の輝きは、今、何世紀もの時の経過を容赦なく見せているボッシュの絵がもともとはどのようなものであったのかということを夢みさせてくれ、我々の目には、何百年も経た後でさえほとんど変質することなく、今日まで、もとのすばらしい色調を保ち続けているような古文書の、驚くべき華麗な細密写本のようにうつる。あらゆる場面で、ボッシュのファンタジックなイマジネーションが、驚異的なほどに忠実に再現されており、既に知っているにもかかわらず魅了されてしまう世界に、我々を沈み込ませてしまう。
|
||
へスス・モレーノ・サンス(文学者、哲学者、文化科学庁) ・・・・・・・・ 瀧梅岡真理子が自分の絵で成し遂げたこの絶妙な試みは、この「観点」からこそ理解されるべきだと、私は考える。つまり、東洋と西洋の技術・様式を非常に日本的な方法で錬金術的に混ぜ合わせて、闇を透かし、闇に傷をつけるという深淵を覗くような彼女の内面的な行為そのものによって、自己の最も奥底の知覚認識と、光りの最も「外側」の面とを合流させる色の舞いや虹を通して、光りの行為の純粋なしるしを表現しようと探し求めているのだ。魂そものの光りとふさわしい形で調和する。より「自然」な光りの焦点的な集まりに対するこの愛着の念を理解するには、あの偉大なる谷崎潤一郎と彼の作品「陰影礼賛」について考えないわけにはいかない。つまりこれは光りの儀式であり、神の恵みの暁光と暗闇との間に、色の橋をかけるという挑戦を受けて立った絵なのだ。 ・・・・・・・ 瀧梅岡真理子の絵は、道教の言葉で言えば、「心の断食」をやり遂げたのだ。たぐいまれなこの画家のあらゆる絵に描かれている、生れ出ずる光の持つ途方もないほども静寂・・・とでも言えようか・・・の中に、既に、彼女自身の透き通った夜を描き出すことを可能にしている魂と目「夜」は欠かすことのできないものなのだ。 ・・・・・・・ 自ら光りを発してしいるのが「グレーの氷解」と、特筆すべき、眩惑されたような「夜のニューヨークへ」の一枚絵だ。そして、二枚の絵のどちらにも「だあれもいない」のだ。
|
||
エドワルド・スビラッツ(プリンストン大学教授、ニューヨーク大学教授、美術評論家、哲学者、文学者) ・・・・・・・ 一芸術作品の技術的模写と造形的再創造というふうに二つの問題があるが、瀧梅岡真理子の作品は、この両極間にある熱く知的な緊張関係をはっきり示している。きちんとした技術的な復元・修復・複製という緻密で繊細な仕事をこなす一方で、ヘロニムス・ボッシュが彼の作品のパネルに表現しようとした精神的テーマに現代性を持たせるということ、即ち、自然と神秘、建造物と彼女のあいだの心情的関係、それに近代文明の持つ無秩序でダイナミックな空間というものを、我々の目に提示しているのである。
|
||
|
||
≪カタログ中のテキストの抜粋≫ |
||
|
陰里 鐡朗(元横浜美術館館長) ・・・・・・・ なかでも<夜の竹里>は私に『竹取物語』を想起させた。月光のなかにある神秘的な竹林とその暗のなかのいくつかの黄金色の輝き。「かぐや姫」の物語りは、日本の古代の貴族社会の風刺であると同時に日本の伝統的な美意識の原型のひとつでもある。この“暗のなかの光”といってよい瀧梅岡のボッシュ体験以降の主題の表現は、この画家がいやおうなくその身にもっている日本の文化的伝統とボッシュの体験との結合から生まれているように私には思われる。 ・・・・・・・ ボッシュ体験以降後、瀧梅岡の作品は<森>シリーズから<泉>シリーズ、そして<深淵>シリーズ、<夜>シリーズと展開してきている。このいささか速度の早い、矢継ぎ早の展開は壮大な観があるが、そのどれにでもボッシュ的なるものがこの画家の内部に入りこみ、種子となっているように思われる。そしてそこから発せられたエネルギーは絶えず暗と光とが壮大な交錯を創りだしているようである。この暗と光の交錯はこれからなおいっそうの成熟をもつのかもしれないが、ボッシュ体験がこの画家に大きな飛躍をもたらしたことは疑いない。この壮大な交錯に、時代と人間、昼と夜、陽光と月光、そのなかに浮遊する現代人の魂をみることができるかもしれない。
|
||
中谷 伸生(関西大学文学部教授、美術史家) 画家にしろ彫刻家にしろ、芸術家は生涯に一度か二度、神がかりのような精神状態に陥って、天与の一作というべき作品を創造することがある。ゴヤの「1808年5月3日」(1814年)、あるいはアントニオ・サウラの「ゴヤの犬」(1984年)はその代表例であろう。ここで紹介する瀧梅岡真理子の「ボッシュ礼賛」もまたその好例だといってよい。ボッシュの「快楽の園」が、宝石を散りばめたような鮮やかな<陽>の天国と地獄を示すとすれば、梅岡の「ボッシュ礼賛」は、モノクロームの<陰>の天国と地獄である。テンペラと油絵の混合技法によるグレー一色の「ボッシュ礼賛」(1997年)は不思議な透明感を見せる静謐な作品だといってよい。主題、モティーフ、色彩、タッチ、加えて、日本東洋の絵画や書など、過去の芸術作品の伝統を画中に織り込みながら、梅岡はいともあっさりと画面を仕上げた。 ・・・・・・・ ボッシュ没後に、ボッシュ絵画を見た人物は山のようにいるが、ボッシュに直接会った人物は梅岡以外にはいない。その奇跡の体験が、東洋と西洋の文化的枠組みを超えた「ボッシュ礼賛」を生みだした。 ・・・・・・・
|
||
瀧梅岡 真理子 1987年7月、あんなにも避けていたスペインに自分の絵が瀕死の状態にあることを感じ初めて足を踏み入れる事になった。何故そんなに避けていたのかと言うと、それまで見たこともないのだから何の根拠もないのだが、ある直感があってどうしても関わりたくなかった。自分の絵に起こった問題の出口を探しているうちにグレーの時間をさまようようになり、ここから脱出するには、今まで避けていたものに接する事、嫌だと思ったところへ行き、嫌だと思った事を全部したら可能かもしれないと思い、決心した。 ・・・・・・・ そして、プラド美術館を歩き回り、私は本当は前から知っていた結果の前に立ち止まり、やっぱりこの苦い杯をイエズスのように飲まなくてはならないのかとため息をついた。もうどう考えても疑いようもなかった。ボッシュ作快楽の園の中にこの扉を開ける鍵がある、そんな確信を持てることなんて、人生の中になかなかないし、すべての画家に与えられるものではないので、ついに決心した。 ・・・・・・・
|
||
ハビエル・ルイス(スペイン外務省セルバンテス基金研究所エジプト所長・考古学者) ・・・・・・・ 瀧梅岡真理子は、5年の歳月をかけてボッシュの「快楽の園」を考察にし、研究し、そして、描くという比類のない課題に没頭した。これは芸術そのもの自体より芸術を生み出すという現代における芸術の範疇に完全に位置するものである。この期間、梅岡は常に謎に包まれたこの庭園の危険な道を散策したが、生粋の日本人の態度でもって、禅仏教の枯山水を思い起こす構成の下に、作品に透明な水、露及び湿り気というものを再現した。ボッシュ特有の雰囲気の中で画業に専念し、梅岡はとっておきの日本芸術の秘密を本来の伝統の外においていかに効果的に作用せしめるかということを我々コンテンポラリーの傍観者に打ち明けている。湿気、乾き、無の空間、雲も池も噴水も真の水を含んでいるわけではないが、それはあたかも本物のボッシュが丁度アトリエから出て来たみたいである。刷新されたボッシュであり、我々と同時代のものに見事に変わり、現代と同じ本性に駆り立てられて創作している。このことは、新しい「快楽の園」の創作者瀧梅岡真理子をして非常に現代的な作家にしている。
|
||
アントニオ・フェルナンデス・デ・アルバ ・・・・・・・・ 多くの犠牲を払い、自分自身の内面からの認識に満ちた、描くという行為に於いて、絵のデッサンに時間を惜しむことはできない。生れ出た絵は、心の奥底を写すような線描のメタファーや、ベールに被われた幾何的輪郭や、夜のうちにかすかに姿を現す星座のみが小さな光の穴を開ける暗い森や、奪回された時間的宇宙や、平行六面体の大都市や、思い出のしるしを伴った事物の素描や、あるいは、忘却のかなたの薄闇の中の生命の謎とその本質にも広がっていくのである。
|
||
イグシオ・ゴメス・デ・リアニョ(コンプルテンセン大学教授〔美学〕、文学者、美術評論家) ・・・・・・・ 瀧梅岡真理子の手になる、ボッシュの「快楽の園」の、クリスタルガラスのような驚くべき複製を見ながら、私は全身質問の固まりであった。この日本人の女性画家がこれほど執拗に捜し求めてきたものは何なのか。ある挑戦に対する答えを出したかったのか、それとも、ものすごく奇抜なことをやりたいと考えたのか。多分、ボッシュがたどったプロセスを再び体現しようとしたのではないか。 ・・・・・・・・ 真理子はあの原型をもう一度具現化しようと望み、彼女の筆があふれるように生み出す曙のような風景を生き生きと感じとることで、楽園の新しい女主人であるかのように感じたのではないだろうかと、私は心の中で問いかけていた。 ・・・・・・・・ 「園のどの部分が最もよく自分を表現していると思う?」と聞いてみた。
|
||
マヌエラ・メナ(国立プラド美術館前副館長、現パトロナート) プラド美術館にあるボッシュの絵の、瀧梅岡真理子による巨大な模写作品快楽の園は、最初、信じ難いものをみているという驚きの念を起こさせる。時間に追われ、一瞬の感情に左右されて動く現代社会にあって、昔の絵の師匠(マエストロ)、それも、几帳面で精密で、細部にまで気を配り完璧家であった中世のフランドルのマエストロが持っていたような名人芸、辛抱強さ、根気を持つ者がいるなどと信じることができないのである。この大変に若く並外れた日本人画家の、偉大なるトリプティカの色調の輝きは、今、何世紀もの時の経過を容赦なく見せているボッシュの絵がもともとはどのようなものであったのかということを夢みさせてくれ、我々の目には、何百年も経た後でさえほとんど変質することなく、今日まで、もとのすばらしい色調を保ち続けているような古文書の、驚くべき華麗な細密写本のようにうつる。あらゆる場面で、ボッシュのファンタジックなイマジネーションが、驚異的なほどに忠実に再現されており、既に知っているにもかかわらず魅了されてしまう世界に、我々を沈み込ませてしまう。
|
||
フェルナンド・R・デ・ラ・フロール(サラマンカ大学教授) ● レプリカの心 ・・・・・・・ ボッシュについて語りボッシュの世界に入り込もうとする時、瀧梅岡真理子の作品がもたらす神秘と魅惑を決定的な力強さをもって感じるのです。彼女独自の定義づけ、現代感、ボッシュの夢の上に重なった彼女自身の夢などが我々を呼び止めるのです。 ● 模写する、複製する、創造する ・・・・・・・ ある意味で、この綿密な地図製作者の役割を瀧梅岡真理子が行っているのです。天地創造的な途方もない大きな仕事を実行したのです。 創造というものは倒錯した意地の悪いものに違いありません。見る者は困惑してしまうからです。今日、創造という問題に関して新たに深く考え直してみるべきだと思います。彼女がその問題を投げかけています。その答えとして、彼女は彼女の文化の特徴である意図するものの静寂さと不可侵さを与えてくれます。その文化は、空間と時間という法則の不安定さに常に根ざしているのです。 ● 仮の終わり ・・・・・・・ 偉大な現代人アンディ・ウォーホル(Abdt Warhol)の逸話が一番よいでしょうし、今のお話ししてきた事と重なります。1985年の某日アンディ・ウォーホルがマドリッドを訪問中プラド美術館での逸話です。ウォーホルは世界で最高の美術館プラドの広い展示場をいくつも見てまわっていましたが、どの絵画の前にも足を止めませんでした。しかし、謙虚に、模写しているある画家の姿を見て(おそらくボッシュの絵にも感動して)その歩みを止めました。そして、この(瀧梅岡真理子の)現代作品を眺めたのでした。 この逸話は“時の矢”の問題を新たに考えさせます。シークエンス(順序)、起源、模写、再生に関して我々が抱いている実際の思考範疇の問題です。真理子の作品が厳しく訴えている問題です。 ● 本当の終わり(最後の最後) ・・・・・・・ ある種の悪の連想は浄化されます。ついには下品な物体は破壊されるのです。古いものは新しい力に取って代わられます。そしてそこからひとつの新しい存在が始まります。 国王フィリップ2世がエル・エスコリアルの闇の中で贔屓にしていたボッシュの絵をやっと手に入れ眺めた時受けたでもあろうボッシュからの古いメッセージは、この明るい“日本協会”において1999年11月末、瀧梅岡真理子が我々に送っているメッセージとは完全に異なり遠いものになっていると我々は感じることができます。 錬金術の手法が実行されたのです。 作品は変換したのです。世界におけるその作品の本質や置かれた状態を変えることによって作品は新しいものに変化したのです。確かにそう言えるのです。
オプス・ノヴム!! (新しい作品)
|
||
エドワルド・スビラッツ(プリンストン大学教授、ニューヨーク大学教授、美術評論家、哲学者、文学者) ・・・・・・・ 一芸術作品の技術的模写と造形的再創造というふうに二つの問題があるが、瀧梅岡真理子の作品は、この両極間にある熱く知的な緊張関係をはっきり示している。きちんとした技術的な復元・修復・複製という緻密で繊細な仕事をこなす一方で、ヘロニムス・ボッシュが彼の作品のパネルに表現しようとした精神的テーマに現代性を持たせるということ、即ち、自然と神秘、建造物と彼女のあいだの心情的関係、それに近代文明の持つ無秩序でダイナミックな空間というものを、我々の目に提示しているのである。
|
||
エウヘニオ・グラネル(シュールレアリズム画家、E・グラネル財団会長) 日本人画家、瀧梅岡真理子はプラド美術館に於いて、かの創意あふれた大人物ヒエロニムス・ボッシュが夢想した究極の謎の世界である「快楽の園」と呼ばれるトリプティカを模写(この上なく見事に)するという、大胆で根気強い仕事をやり遂げた。 この若い女性画家は、彼女の書いた「ボッシュとの出会い」とい文章の中で、スペインへ何度もやって来た時の状況や、ベルスケス、スルバラン、ゴヤの絵に対して抱いた興味、ボッシュの時代に使われていた絵の具を使いこなすという、非常に困難な作業をやれるようになるまでの訓練課程や、ボッシュの巨大な画面の再現に専念した5年間というもの、毎日プラド美術館でどのような方法で描いたかということを述べている。 マドリードのシルクド・デ・ベジャス・アルテスに於ける絵画展の初日にその「快楽の園」の模写作品を見た時、私はそのあまりにも正確に写された透明な鏡を前にして驚くと同時に、このフランドルの画家の作品に関するあることを思い出していた。 ・・・・・・・ 瀧梅岡真理子の才能はその根気強さとあいまって、再びその期待を呼び起こすこととなった。彼女のおかげで、ボッシュはその素晴らしいイマジネーションの輝きを、再び私のもとへ運んで来てくれたのである。 「快楽の園」の模写作品によって、瀧梅岡真理子は芸術世界にこのうえない贈り物と教訓をもたらしてくれた。この見事な絵は世界中で鑑賞することができるため、本物の絵がピカソの大作「ゲルニカ」が受けたような、ほとんど破滅的な損傷を受けなくてすむことになる。このように大きな絵は、現在展示されている場所から動かすべきではないと思う。ボッシュの絵のレプリカがたった今誕生した。この絵は、古くならないうちにどこへでも旅することができる。 瀧梅岡真理子は優秀な画家であるばかりか、優れた作家でもある。愛の表現に関する金言句のような瀧梅岡真理子の文章は貴重な文章である。 ・・・・・・・ 瀧梅岡真理子の風景の持つ謎めいた雰囲気は、疑いもなく彼女が理想とするこの巨匠の精神を不思議にも受け継いだことによるものにちがいない。また、二人の大胆さがお互いを結びつけてもいる。「夜の竹里」と題された作品は、「快楽の園」に描かれたあらゆる光景を、中に閉じ込めたり開いて見せることのできるようにした画板の上の半円の中にボッシュが描いたものと関連を持っている。このことは、瀧梅岡真理子の模写作品を、単なる模写以上の驚嘆すべき透明な鏡としているのである。
|
||
|
||
≪カタログ中のテキストの抜粋≫ |
||
フェリクス・ルイス・デ・ラ・プエルタ(マドリード理工大学建築学部教授・哲学博士) ・・・・・・・ この画家が選んだ道、中道という道はたやすくもなく心地よいものでもなかった。しかし良き仕事とその作品の質の高さによって、タキウメオカは名だたる現実主義派の中にその位置を占めることができた。J.ポロックの作品の場合はその表面を埋め尽くしているのはラインであり、M.ロスコーの場合にはカンバスを支配しているのが陰影であるとするならば、タキウメオカの作品から迫り出してくるのは世界の闇である。タキウメオカの作品はアメリカ的な抽象的表現主義の理念には組しないが、テクニックと表現法ではこのグループとの類似点を持っている。また具象絵画とも異なり、その風景については、森や川などの自然のエレメントは最大限に抽象的に描かれているのだが常に現実のものとのコネクションを維持している。よってこの見地からすると、タキウメオカの作品は抽象的リアリズム、あるいはむしろ関西大学教授の中谷伸生氏が言うように「表現派的抽象」に分類できるだろう。 ・・・・・・・ 彼女が森をテーマとしている場合、見るものを、深く力強い、だが確定されていない自然の前に立たせる。タキウメオカの絵は常に私たちをスタート地点、始まりに連れてゆく。この後もどり、過去へのこの回帰は時間の向きを変えさせ、空間に置かれて物体相互の関係を変化させる。
|
||
|
||
≪パンフレット中のテキストの抜粋≫ |
||
|
中谷 伸生(関西大学文学部教授、美術史家) ・・・・・・・ 瀧梅岡真理子の代表作「ボッシュとの会話」は、西洋文化のひとつの源泉であるネーデルランドの画家ヒエロニムス・ボッシュから霊感を得た大作である。
以後、瀧梅岡はボxxフの神秘的な中世世界に入り込む作品へと向かうことになる。
そこでは、平安時代の精神文化が、現代の形象という衣をまとって蘇る。
国際的視野を持つ日本人画家の瀧梅岡は、日本の文化を世界に解き放ち、東西の芸術的世界に橋を架けようとしている。
|
||
|
Mariko Takiumeoka Web Site